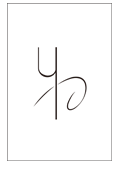chef's story VOL.4
恵比寿ガーデンプレイス内にあるシンボル的な建造物“シャトーレストラン・タイユヴァンロブション”(現“ジョエル・ロブション”)当時フランスの三ツ星“タイユヴァン”と“ロブション”が一つの館で最高の料理とサービスを提供するという、前代未聞の世界六ツ星として話題をさらっていた。
噂を聞きつけたグルメたちで溢れ、オープン当初から半年後まで既に満席といった状態が続いた。
毎日昼夜100名のゲスト。週末となればその倍のゲスト達でにぎわう。
そんな調理場内の過酷さは、想像をはるかに超えたものだったに違いない。
日本各地から集まった優秀なキュイジニエ(料理人)たちは、そんな過酷な毎日の中、団結心を強くし、テクニックだけでなく、ありとあらゆるものを習得していったのであろう。
その証として、当時のメンバーは日本各地にとどまらず、世界各地で活躍中である。
まさしく食べ手にとっても作り手にとっても夢のレストランであったに違いない。
それは22歳で上京し、フレンチレストランで修行をはじめた浅井シェフにとっても同じであった。
そして“タイユヴァンロブション”の中核となるまで力をつけていたのだった。
しかしそんな矢先、浅井シェフはオープニング当初からの疲労が重なり、身体を壊し、過労で倒れてしまう。
医者からストップがかかってしまったのだ。
覚悟はしていたものの、浅井シェフにとって病室は別世界、青白い天井を見上げながら
「自分は復帰できるのだろうか?」
「もし戻れたとしても自分の居場所はあるのだろうか?」
と毎晩不安な夜を過ごすことになった。
「ふと考えては連日連夜戦場のような調理場の光景が頭をよぎっていました。そして仲間は頑張っているのに自分はベッドの上…と、やりきれない気持ちでいっぱいでした。」
と、その時のことを語っている。
退院し、復帰はするも、すぐにポジションチェンジを言い渡され、なれないポジションで部門長を務めることになる。
だが問題が続出してしまう。さらに仕事は半端になく多い上、他のポジションよりスタッフも少なく、とても足りない…
その辛さのあまり後輩たちは去っていく一方だったのだ。
スムーズに仕事を回すのも困難な環境、通院しなければならないというハンデ、病み上がりで発揮できない本来の力。
そんな無残な状況に置かれた浅井の評価は下がっていった。そしてついには昇格の先送りまで宣告されるのである。
でも浅井シェフは腐らず負けなかった。自分はやる。いや、できるんだ。今は我慢の時だと・・・
そんな時、浅井シェフに救いの手を差し伸べたのが河野氏だった。
『料理コンクールの出場の要請』それは浅井シェフのスランプを気遣う河野氏の優しさかもしれなかった。
しかし即答できないでいた。「現状の仕事でこんな状態なのにコンクールに出場している余裕はない」と。
しかし、その一方で「だが何もしなければ依然として出口も見えない…」とも思っていた。
そして次第に「もう一度自分を奮い立たせるチャンスかもしれない」という考えが頭の中を支配するようになり、
ついに浅井シェフは河野氏にコンクール出場を申し出る。締め切りギリギリの日だった。
連日机に向かい料理のスケッチとレシピを完成させ、一次審査を通過。
今の自分の可能性へのチャレンジという別のテーマが彼にはあったのだ。
休日も返上して試作を繰り返し、河野氏に味をチェックしてもらう。OKをもらうたび自分を高めていく。
そして“タイユヴァンロブション”の看板を背負い出場した結果、見事準優勝に輝いたのだった。
浅井シェフは少しずつ自信を取り戻していった。それが仕事にもつながり、シェフやスタッフの信頼も徐々に戻り、昇格も果たした。「人間的にも大きく成長できた時期です」と浅井シェフは振り返る。
円熟の域に達した27歳のとき、再び浅井シェフに転機が訪れた。
10年来の付き合いになる河野氏が“タイユヴァンロブション”の日本人シェフという立場を辞め、独立するというのだ。
上京して以来、ずっと自分を見守ってくれていた河野氏。フランスに行くこともできたのも、話をつけてくれた河野氏のおかげ。
いよいよ自分にも恩返しが出来る時がきた。浅井シェフに迷いはなかった。自分がどこまで役立てるのか。
そして現在ミシュランで一つ星に輝く“モナリザ”のスーシェフとして裏舞台を一手に引き受けることになる。
「とにかく河野シェフに成功していただきたかったんです。ただそれだけの想いでした」と浅井シェフは熱く語った。
“モナリザ”の立ち上げに大きく貢献した浅井シェフは、大きくステージを変えることになる。
地元名古屋の老舗レストランの料理長という要請を受け、一次、名古屋へ戻ろうと決意したのだ。
chef's story VOL.5>